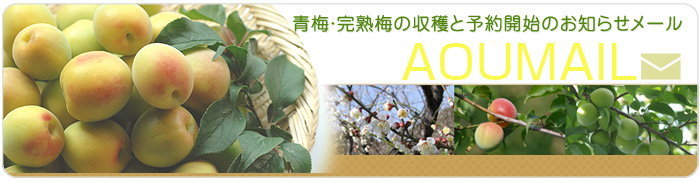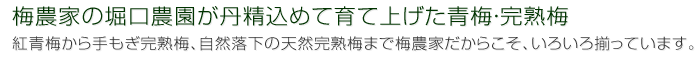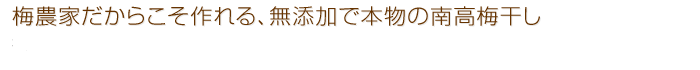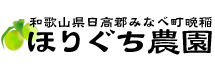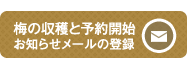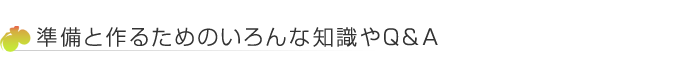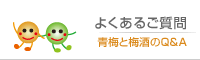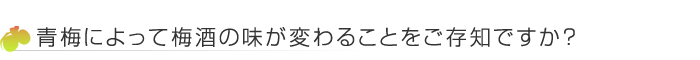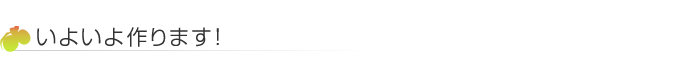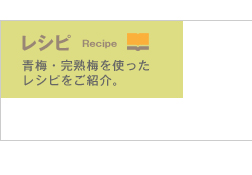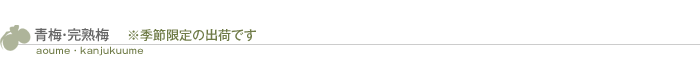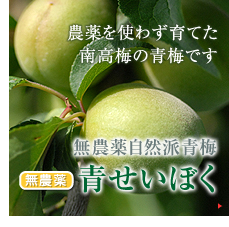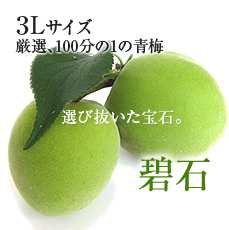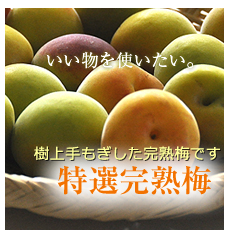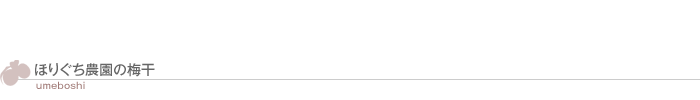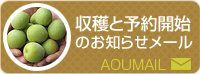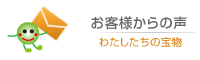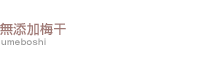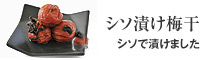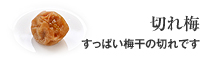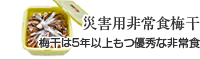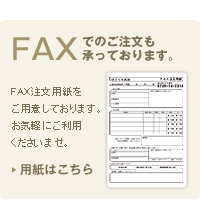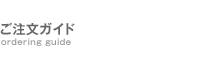ホーム > 梅酒の作り方

暑い夏に涼しい縁側で氷を浮かべた梅酒を楽しむ
自分で作った梅酒を楽しむ
それは、自分で作る人だけの贅沢
青梅にこだわって梅酒を作る
漬込むお酒にこだわって梅酒を作る
寝かせておく時間にこだわって梅酒を作る
こだわりかたは人それぞれ
さて、今年はどんな梅酒を作りましょう・・・・・・・
ここでは梅酒の作り方をご説明
説明してある手順どおりにやるのがコツ
ポイントを押さえれば梅酒の作り方は簡単です

| ■材料(標準量) | ||
| 青梅(紅青梅) | 1kg | 梅の風味を強めるのなら、青梅はあと100g程度なら追加してもOK。 |
| 氷砂糖 | 500g | 甘い目がお好みなら氷砂糖は1kgぐらいまでなら増やしても大丈夫です。 |
| ホワイトリカー | 1.8リットル | アルコール度数が低い(35度未満)お酒は避けたほうが無難です。 |
| 5リットルビン | 1個 | ふたがきちんと閉まるもの。ホームセンターなどで手に入るものでも充分です。 |
| 竹串 | 2〜3本 | 青梅のヘタを取るのに使います。金属製はだめですよ! |
- 梅酒を作る時のお酒はホワイトリカー以外に日本酒とか焼酎を使ったらダメなの?
- ホワイトリカーは果実酒を作るためのお酒で、何度も蒸留して作るのでほとんど無味無臭です。
だから梅の風味が活きます。でも、ほかのお酒でもぜんぜんOKです。ただ一つ注意して欲しいのが、アルコール度数が35度以下になると、梅の成分が抽出されにくくなり、熟成も進みにくくなります。
だから、ほかのお酒を使うときはアルコール度数に注意してください。
アルコール度数が低いお酒を使うとカビが生える危険性がありますからご注意を! それとあんまりクセのあるお酒は梅の風味との相性を考えてね。 - 氷砂糖の代わりに普通のお砂糖や、黒砂糖やザラメ砂糖なんかは使えないの?
- 使えますが色々とポイントが変ってきますし、味にクセが出てきます。
それを承知で使うというのなら問題はないと思います。
(黒糖で作ったけど甘みがないというご質問をいただきます。調べましたところ黒糖はふつうのお砂糖に比べて甘さ控えめだそうです。お砂糖の特徴によって出来上がりや作り方のポイントが変わってまいりますのでご注意くださいね。)
氷砂糖を使う理由は、先ず一つ目に砂糖としての純度が高い(雑味が少ない)ということです。 さきほどのホワイトリカーのときにも書いていますが、クセの強いものは梅の風味を損ねます。
それに氷砂糖はゆっくり溶けるので、梅の成分がしみだしてくる速度とバランスがいいと言われています。
一番の理由はやっぱり溶ける速度ですね。 - お砂糖類を一切使わないで梅酒を作ることは出来ないの?
- できます。砂糖類を一切使わないで梅酒を作ることは出来ますが、浸透圧が変ってきますので、糖類を使った場合より梅の成分の抽出に時間がかかります。
- こだわりの梅酒を作ろうと思います。お勧めの青梅を教えて
- 青梅の熟度によってお味がかわってきますので、下記表を参考にお好みの味をみつけてくださいね。
| きりっとしたお味 | プレーンなお味 | まろやかな味わい |
|---|---|---|
| 翠珠4Lサイズ(通常) | 琥珀珠4Lサイズ(まろやか) | |
| 碧石3Lサイズ(通常) | 琥珀珠3Lサイズ(まろやか) | |
| 無選別青梅(きりっと) | 無選別青梅(通常) | 無選別青梅(まろやか) |
| 青せいぼく | 緋珠 | |
| 紅石 | ||
| 無選別は基本的に2L〜3Lサイズまでのばらつきがあることと、小粒のものは果肉が少ないため味にばらつきが出やすいのが特徴です。翠珠(4L以上)、碧石(3L)、紅青梅の紅石・緋珠・琥珀珠は3L以上のサイズの特別品ですので果肉も厚く果汁の量も多めになります。 | ||

![]()
先ずはビンを清潔にしてください。
その後きれいなフキンで水気をふき取り、ビンの口を下にして、完全に乾燥させます。
※水気が残っているとカビが生えやすくなりますので、完全に乾燥させるようにしてください。

![]()
青梅をきれいに洗います。
流水で洗うのがいちばんいいです。
洗剤とかは絶対に使っちゃダメですよ!
丁寧に丁寧にお水で洗ってください。

![]()
洗ったらたっぷりのお水(2リットル以上)に漬けてアク抜きをします。
青く硬い実は1時間から2時間程度が目安、これをおろそかにすると梅酒に渋みが出ます。
樹で熟す間に青梅の中に含まれるエグ味の成分が消えてくるということがわかりましたので、ほりぐち農園の無選別青梅(きりっと)以外はあく抜きをしなくても大丈夫です。つけても1時間までです。(完熟梅は劣化の原因となりますのであく抜きはしないでください。)

![]()
アク抜きが終わったら、きれいなタオルで水気をふき取ります。
さきほどのビンのときと同じで水気はきっちり取っておくのがポイントです。

![]()
水気をきれいにふき取ったら、竹串を使ってヘタを一つ一つ丁寧に取り除きます。
竹串を使う理由は梅は金気(金属)を嫌うといわれているからです。
別に金串を使ってもいいのかもしれませんが、ここは雰囲気を楽しむためにも竹串を使って一つ一つ丁寧に取りのぞきましょう。
きれいに取れば取るほど梅酒にエグ味がなくなりさわやかな味わいになっていきます。
綺麗に取れば取るほど美味しくなるのです。さらに取りながら「美味しくなあれ!」と念を込めればさらに美味しくなること間違いなし!
あと、梅を竹串で突いて穴をあけるという人もおられますが、別に穴をあけなくても大丈夫。浸透圧の関係で梅の成分はきちんとしみだしてきます。ほりぐち農園では毎年梅酒を作っているのですが特に穴をあける必要性は感じていません。

![]()
青梅と氷砂糖をそれぞれ半分に分けます。
半分に分けて2回分にして、2回に分けてビンに入れていきます。
- 青梅を入れます。放り込むとつぶれちゃいますから丁寧に。
- 氷砂糖を入れます。上から降りかけるような感じで入れます。
- 残りの青梅を入れます。先ほどと同じで丁寧に入れます。
- 残りの氷砂糖を入れます。これも先ほどと同じで振り掛けます。
量が多い場合は分ける量をふやしてみてくださいね。

![]()
さて、いよいよホワイトリカーを注ぎます。
ドバーっといれちゃっていいですよ。
一気に注ぎ込んでしまっても大丈夫!
今回使っているホワイトリカーは同じ和歌山県の中野酒造さんのホワイトリカーです。
梅酒で有名な酒造会社さんで、大阪天満宮で開催された梅酒グランプリで大賞を受賞した実績もあるんですよ。
そこのホワイトリカーだから大丈夫!
というわけで毎年使わせていただいています。
酒税法の規定で自家製梅酒を作る時はアルコール度数20度以上のもので漬けなければなりません。

![]()
こうして梅酒を漬け込んだら、あとはきっちりとフタをして温度差のなるべく少ない涼しい場所で保存します。
約6か月後から飲み始めていただけます。私たちは梅の花の咲くころからが美味しいということで2月ころから飲み始めます。
梅の成分はホワイトリカーへ入ったり梅の実へ入ったりと行ったり来たりしていりうそうですが、約1年半てば、実から成分が出てお酒にとけこんでいるそうです。長期保存をされる方は約1年半たてば、梅の実を取り出してください。
取り出した梅の実は、そのまま食べてもすごく美味しいですよ。ただ、アルコールが入っていますからお子様には食べさせないほうがいいかも・・・・
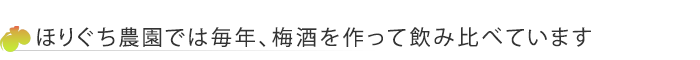
 ふっくらぽってりした青梅や完熟梅で毎年、「辛口の梅酒」と「プレーンな味」と「甘めの梅酒」を作っています。
ふっくらぽってりした青梅や完熟梅で毎年、「辛口の梅酒」と「プレーンな味」と「甘めの梅酒」を作っています。
収穫時期によって実の熟し具合が違いますので、梅酒の味もそれにともなって違ってきます。飲み比べると楽しいですよ。
毎年ホワイトリカーで漬けていましたが、お客様で焼酎で漬けるかたが多くいらっしゃったので、初めて麦焼酎で漬けてみたりと、梅酒作りの楽しさを実感しています。また泡盛と青梅(まろやか)の相性が良いと教えていただいたので、今年漬ける予定です。

![]()
こちらの「緋珠」、「紅石」です!
梅酒を作るなら、ぜひ味わって頂きたいのが、紅がさした青梅の実を厳選した「緋珠」「紅石」。深いコクがあり、味わい深いお味に仕上がります。ゆっくりと、じっくりと、楽しみたいお味です。(写真は「緋珠」を追熟させたものです。)
和歌山県農林水産総合技術センターが、和歌山県産「南高梅」の機能性成分に ついて調べた結果、日光をたくさん浴びて紅色に着色した梅で梅酒を漬けると「クエン酸」「ポリフェノール」、抗酸化能がアップしたと発表しました。